
三味線ってどんなもの?〜形・色・小物〜

三味線方の栄之丞です。
今日は楽器や道具のことについてお話しします。
まず三味線本体です。

長唄の場合は細棹三味線(棹が一番細いもの)を使用します。
三味線の音曲の種類によって使用する三味線も異なります。
例えば義太夫の三味線では太棹三味線を使用します。

棹の部分の太さ、胴(ボディの部分)の大きさ、糸の太さなど全体的に長唄で使用するものよりも大きいのがわかるかと思います。
次に撥です。

練習用の撥は木でできた撥を使用し、舞台などの本番のステージの時は象牙の撥を使用します。
この撥の握り方、使い方は初心者の最初の壁であり、三味線弾きなら生涯悩み続け研究していくものになります。

次は駒になります。(写真左)
様々な素材がありますが、舞台や本番のステージで使用する時は象牙の駒を使用します。この駒の素材によって音色が大きく変わります。
次は指かけです。(写真真ん中)
左手の人差し指と親指にかけて使用します。演奏する上で棹の上下の動きをスムーズにするために使用します。
次は膝ゴムです。(写真右)
右腿に乗せてその上に三味線をのせます。滑り止めのような役割です。
胴にそのまま貼って使用する膝ゴムシールもあります。
ひとまず今回はここまでご紹介しました。次回は糸や譜面などについてお話しします。
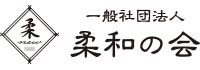










この記事へのコメントはありません。